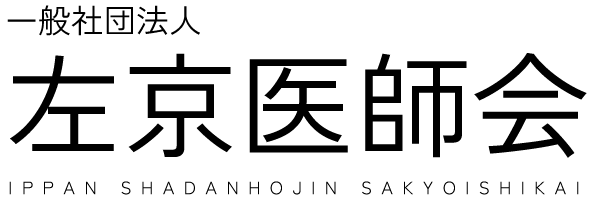認知症部会
認知症部会
わが国が超高齢社会に突入する中、認知症は地域医療において重要な課題のひとつとなっています。令和7年には、団塊の世代がすべて75歳以上となり、いわゆる「2025年問題」の節目を迎えました。認知症の有病率は当初の「65歳以上の5人に1人」という予測にはまだ達していないものの、医療・介護の需要増加や介護人材不足など、認知症をめぐる社会的課題はすでに顕在化しています。
こうした状況を踏まえ、左京医師会では地域の皆さまが安心して暮らせる体制を整えるため、「認知症部会」を設けて、医師・介護職・関係機関と連携しながら、さまざまな取り組みを進めています。
認知症部会の活動内容
左京医師会認知症部会では、会員医師の研鑽と相互交流を目的に定例会を開催しています。
定例会では、医師会員や認知症診療に関わる多職種の支援者を講師として、ミニレクチャー形式で実践的な学びを提供しています。地域の現場で培われた知見や経験を共有することで、日常診療や支援活動に直結する内容となっており、参加者同士の交流や医療と介護の連携の促進にもつながっています。また認知症部会では、左京医師会認知症研究会の企画・運営も行っています。認知症研究会は、診断・治療・ケアに関する最新の知見を学ぶ場として、各分野で豊富な経験を持つ専門家を講師に迎え、講演やディスカッションを通じて理解を深める機会となっています。
※認知症かかりつけ医リストに情報を掲示されている先生方で、内容に変更、追加がある場合や、新規に掲載を希望される先生方は、認知症部会担当理事、もしくは左京医師会事務局までご連絡ください。
認知症かかりつけ医の取り組み
左京医師会では左京区での認知症診療の円滑化のため「認知症かかりつけ医」を設定しそのリストを公開しています。
「認知症かかりつけ医」は認知症患者さんの日常診療を担う主治医として、ご家族や介護関係者の皆様からのご相談をお受けしています。また、左京医師会認知症部会に参加し、疾患や治療に対して研鑽するとともに認知症を取り巻く諸問題に対し熱心に取り組んでいきます。
必要に応じて、初期の鑑別診断やBPSD発症時の対処を行える認知症診療支援医や認知症サポート医と連携しています。
介護保険申請時には、主治医意見書の作成を通じて、医療的な視点から支援の必要性を明確にし、適切なサービス提供につなげています。「認知症かかりつけ医」は左京医師会ケアマネタイムリストにも登録されています。担当のケアマネジャーや関係者の皆様は左京医師会ケアマネタイムリストもご参照いただき、各医師と連絡してください。
地域ぐるみの認知症支援
認知症部会は、医師だけでなく、地域全体で認知症の患者さんを支える体制づくりを進めています。
「さきょう認知症にやさしい地域づくり部会」に参画し、認知症の患者さんやご家族が安心して暮らせる地域社会づくりをめざしています。ここで企画運営される学習会や認知症サポーター養成講座にも、講師を派遣し、認知症の人が暮らしやすい地域環境づくりに貢献しています。
また、左京医師会に所属する認知症サポート医が、左京区認知症初期集中支援チームの活動を指導し、早期診断・早期支援体制の構築に貢献しています。
認知症になっても安心して暮らし続けられる地域をめざし、医療・介護・福祉の多職種と連携しながら、情報の共有・発信と支援体制の強化に取り組んでまいります。